中学生のためのスマートな居残り活動10選
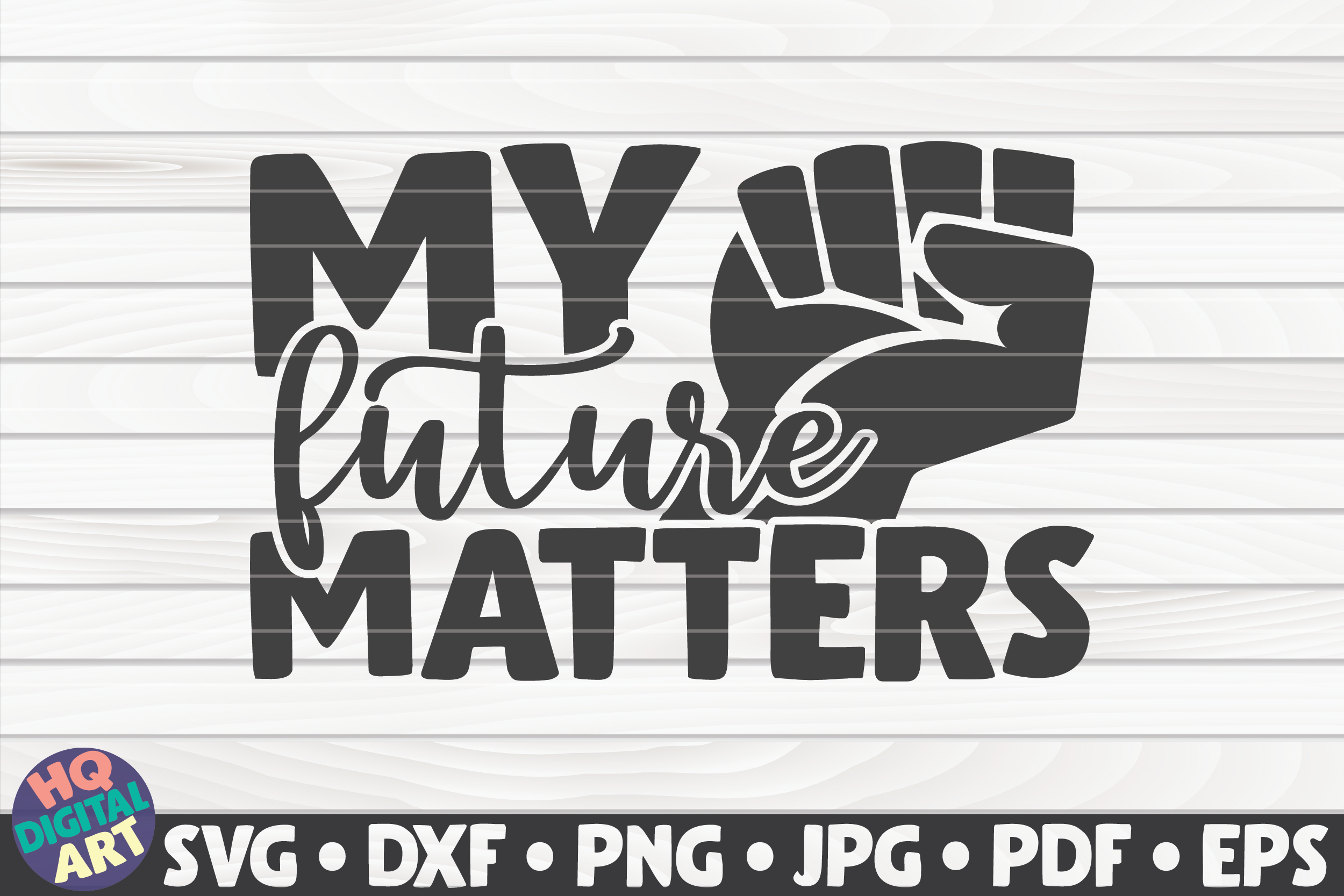
目次
教師は悪代官になるのが好きではありません!居残りは、否定的な行動に対して取るべき懲罰的な手段の一つです。 自分のしたことを振り返る時間です。 これは逆効果です。子どもたちは注意と指導を必要としているから行動するのです。 そこで、居残りに代わるこれらの手段を使えば、教育者はつながり、学生の自信を高めることができます。信頼と尊敬を得て、すぐに居残り部屋は空っぽになります。
1.私の目的は何だろう?
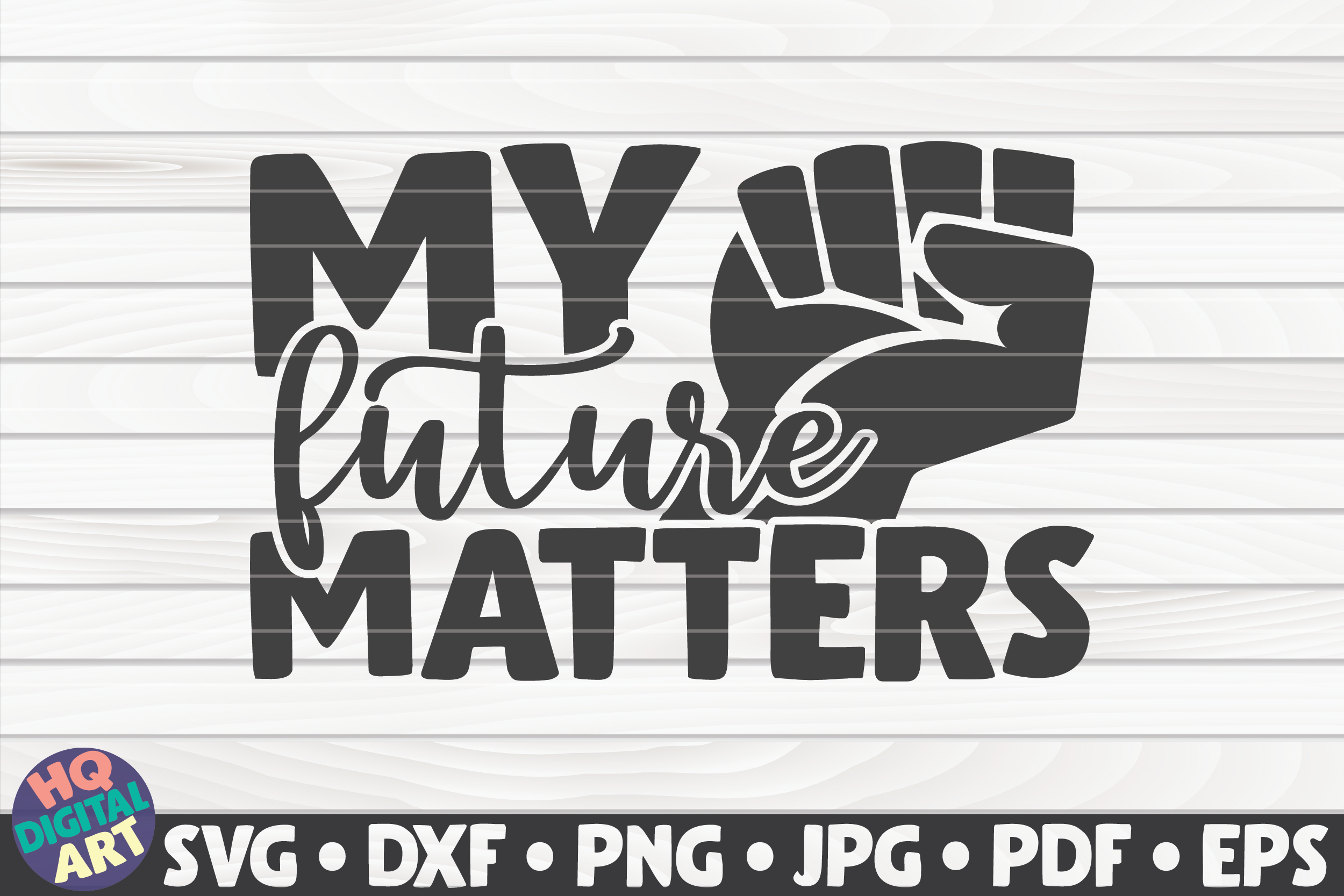
私たちは皆、特別で、独自の特徴を持っています。 子供たちが大きくなるにつれて、彼らが示すポジティブな行動ではなく、ネガティブなフィードバックを言われることが多くなります。 人生はストレスフルで、世界が私たちの周りで変化する中、時々、なぜ自分がここにいるか、そしてなぜ私たちは皆目的を持っているのかを忘れてしまいます。
関連項目: 29 美しい馬の工芸品2.ブラックアウトの詩 素晴らしい指導時間
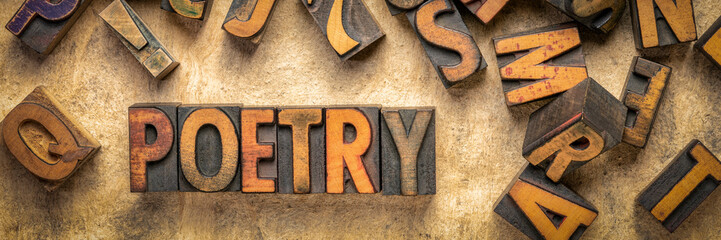
この活動はとても楽しく、誰でも「詩人」になれる、少なくとも挑戦してみようと思わせてくれます。 創作詩に触れたことのない子どもたちは、正解も間違いもないので、これを気に入るでしょう。 これはクールで面白いです。
3.学校の居残りをさせられた
これは、誰かにいたずらをすることが、いかに裏目に出て結果をもたらすかについての面白いスケッチビデオです!居残りの生徒は、いたずらすることがいかに楽しいか、また、リスクに見合わないこともあり、誤った行動によって深刻な結果をもたらす可能性があることについて話すことができます。
4.笑い=ポジティブな校風

これらのゲームは、特に子供たちが安全でリラックスした気分になり、ストレスを発散できるようにするためのものです。 厳しい罰は効きません。 子供たちの会話を引き出すことで、乱暴な行動を減らすことができます 中学校の演劇では、「マッドドラゴン」「会話術」「トーチカ」などがあります!
5.居残り大作戦-反省会
このアクティビティは、子供たちが自画像の制作中に手を使って何かをするのに最適な方法です。 このアクティビティは、子供たちをリラックスさせ、悪い行いを反省させるために、子供たちを安心させることができます。
6.ラップで自分を表現する!
ラップミュージックは中学生の子供たちに愛されており、物事がどのように感じられるかを自分なりのラップで表現します。 "学校は嫌いだけど、授業中に失礼なことはクールじゃない!" このエクササイズは、居残り中に子供たちが発散してストレスを解消する機会になります。 素晴らしいビデオで教育的でもありますね!
7.シンクシート
これらは、生徒のための素晴らしい振り返りワークシートであり、学年ごとに適応させることができます。 簡単に記入することができ、先生やモニターとのオープンな会話につながります。 子どもたちは、次に何をすればよいか、どうすれば争いを避けることができるかを学びます。
8.スマホで刑務所を作ろう!-独創的な留置場のアイデア

携帯電話が教室にあると大変なことになります!教室で期待されることは周知されなければなりませんし、子供たちに携帯電話を手放させるための工夫が必要です。 これらは簡単に作ることができ、携帯電話がなぜ邪魔なのかを示すクラスルールポスターになります。
関連項目: 思わず笑ってしまう、おかしな学校の看板30選!9.昼食の居残り

昼休みは休憩時間ですが、他の子どもたちは居残り給食になり、誰とも顔を合わせず、黙々と食べ、反省することになるかもしれません。 この時間は、栄養学を教え、健康的な食事と自分の行動に責任を持つことについて話す絶好の機会なのです。
10.パンチボール

先生たちは、歯列矯正室でパンチボールを使うと攻撃的な行動が増えると考えています。 逆に、人生は公平でないこともあるので、子どもたちは発散する必要があります。 私たちは何十年も前から古い手段を変え、タイムアウトについて創造的に考える必要がありました。

